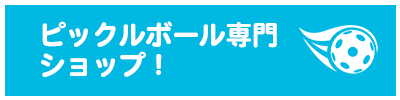プロピックルボール界で今、大きな注目を集めているのが“ライン判定トラブル”。
特にビデオチャレンジが使えないサイドコートでは、選手間での衝突が頻発しています。
今回は、実際に起きた事件をもとに、問題の本質とその解決策をわかりやすく紹介します。
トラブルの発端はラインコール
今回の事件は、PPAツアーの「オレンジカップ」男子ダブルス32強戦で起きました。
プロ選手同士の試合で、問題になったのは、ボールが「インかアウトか」の判断。
ピックルボールでは、選手が自分でアウトをコールできるルールがあり、審判が明確に見えなかった場合は、その判断がそのまま適用されます。
ところが、これが悪用されるケースもあり、「実はインだったのにアウトと叫ぶ」ような場面も。
今回の件もまさにそのパターンで、フェアプレーが問われる出来事となりました。
審判の限界とサイドコートの弱点
大会のメインコート(チャンピオンシップコートやグランドスタンドコート)では、映像判定=ビデオチャレンジが導入されていますが、それ以外のサイドコートでは未導入。
これが問題を深刻にしています。
サイドコートは場所が狭く、観客席も少ない分、注目されにくく、カメラの数も限られています。
審判が1人だけという試合もあり、正確なライン判定を目視で行うのは非常に難しいのが現状です。
結果として「アウトだった」「いやインだ」の押し問答が起きやすくなっているのです。
激戦の中で何が起きたのか?
注目の試合は、レッテンマイヤー&ガーネット組 対 ドーソン&ブラスケビッチ組。
試合は序盤から激しいラリーが展開され、第1ゲームのスコアが2-5-2の場面で事件が起きました。
ブラスケビッチのサーブを受けたレッテンマイヤーが、鋭いスマッシュでウィナーを決めたかに見えた瞬間、ブラスケビッチが「アウト!」と主張。
すぐさまガーネットとレッテンマイヤーは「入ってた!信じられない!」と強く抗議。
しかし、審判は「地面に着いた瞬間は見えなかった」として、判定は覆らずアウトに。
試合はそのまま続行されました。
結局、レッテンマイヤー組が11-3、11-5で勝利したものの、場内には不穏な空気が残りました。
SNSでも話題に!選手同士の因縁
試合後、事態はさらに炎上。
レッテンマイヤーが自身のSNSで「わざとアウトって言った。やられたらやり返す」と投稿。
ブラスケビッチに対して、「本当にアウトだったら2000ドル払う」と挑発するなど、かなり過激な発言をしていました。
しかも、この2人の間には過去にも因縁があり、昨年のMLP(メジャーリーグ・ピックルボール)でも、同様のラインコールトラブルがありました。
その時もレッテンマイヤーは別チームの不正に怒りをあらわにしており、今回の発言はその延長線とも取れます。
選手同士の信頼が揺らぐと、試合そのものの質も下がってしまいます。
根本的な課題と今後の不安材料
プロツアーが成長を続ける中、賞金額は上昇し、さらには今後「スポーツベッティング(※勝敗に賭ける制度)」の導入が検討されています。
そうなると、1本の判定ミスが「数万〜数十万円の損得」に直結しかねません。
しかも、現在のルールでは、ラインの悪質な誤審があっても、その場で証拠がなければ見逃されてしまいます。
ファンからの信頼や、スポンサーのイメージにも影響する可能性があり、競技全体の信用問題に発展するリスクをはらんでいます。
解決に向けた3つの現実的なアイデア
この課題に対して、実際に挙がっている改善案は以下の3つです。
- すべてのコートにラインジャッジを配置する
→人手・スペース不足で現実的ではありません。 - 試合後に映像を用いて不正を罰則で処理する
→効果はあるものの、「その場」で覆せない点が難点。 - 中央ビデオ審判室の設置と、全コート映像監視体制の構築
→各コートに複数カメラを設置し、審判が集中管理するシステム。
初期投資は必要ですが、今の課題に最も実効性のある方法といえます。
今後の公平な大会運営のためには、この第3の案が最有力と考えられています。
まとめ
ライン判定をめぐる問題は、今のプロピックルボール界にとって「避けて通れない課題」となっています。
審判の目だけでは限界がある以上、テクノロジーを導入していくのは自然な流れです。
フェアな試合環境が整えば、選手同士の信頼も生まれ、ファンも安心して試合を楽しめるようになります。
これからのピックルボールが、よりクリーンでエキサイティングなスポーツとして進化していくために、今が変革のタイミングなのかもしれません。