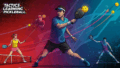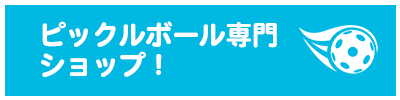決勝の翌日、ベテランのハイメ・オンシンスが週末の戦いを時系列で振り返り。
ふくらはぎの故障から逆転勝ちの瞬間、空き時間の食事や早朝ルーティンまで、実戦に役立つヒントが満載です。
読めば試合準備の精度が上がります。
大会最終日の心境とケガ
試合中、右ふくらはぎに「プチッ」と音がした瞬間にプレー続行が難しくなりました。
本人も過去に反対側のふくらはぎを痛めた経験があり、今回はより症状が強いと判断。
まずはアイシング(※患部を冷やして炎症や痛みを抑える処置)と安静、翌日の再評価が最優先。
「悔しいけど、プレーはやっぱり楽しい」と語り、焦らず回復を優先する姿勢を貫きます。
競技者としての危機管理が光ります。
– ポイント
– 発症直後はアイシング+圧迫+安静(RICEの基本)
– 復帰は段階的に。無理をしない判断がキャリアを守る
バイ明けの初戦と長年の相棒
バイ(※初戦免除)は相手の試合感が温まっているぶん不利にもなる。
そこでアップは通常より5〜10分多めにし、ドロップショット(※相手の足元に短く落とす球)と第三打のパターンを確認。
長年組む相棒マルセロとは、前衛と後衛の役割分担を明確化し、ロブ対応はマルセロ、ドライブの展開はハイメが主導。
初戦は配球の質を上げて主導権を取り、スコア以上に内容で勝ちに行く作戦がハマりました。
– ポイント
– バイ明けは球出しアップで“試合速度”を取り戻す
– 相棒と役割と合図を事前確認して迷いをゼロに
試合後の振り返り術とメンタル
夕食後に「良かった3点・直す3点」を5分でメモ。
翌朝は直す3点のうち1点だけに集中して改善するのがハイメ流。
感情の切り替えは5〜10分で終了し、次の試合にエネルギーを温存。
具体例として、ネット際での不用意なハーフボレー(※弾み始めを低い姿勢で返すショット)のミスを映像で確認し、スタンス幅を広げる修正を翌試合で実行。
若い選手にも真似しやすいシンプルなPDCAです。
– ポイント
– メモは短時間・少項目で“実行できる形”に
– 1試合1改善に絞ると定着率が上がる
決勝の激戦と“大人の競争”
決勝は相手のリターンが鋭く、第1ゲームはリズムを奪われる展開。
第2ゲームはサーブのコースを体側中心に寄せて、相手のバック側へ集中的に配球。
終盤にミニドラマ(接触や判定への意見)がありつつも、「コートのことはコートに置いていく」が全員の共通認識。
握手で締めてリスペクトを示し、明日に向けて心と体をリセット。
勝敗を越えた態度が、競技の価値を高めます。
– ポイント
– 追い上げ時は配球の“的”を絞って圧をかける
– 終了後は相手・審判への敬意を忘れない
長い空き時間の調整法とシニアの誇り
長い待機は血糖値の乱高下が敵。
ハイメはプロテインシェイク(※消化に優しく素早く栄養補給できる飲料)+バナナ半分で軽めに維持。
第1ゲームでエラーが増えたら、テンポを落としドロップ→ディンク(※ネット付近で小さくつなぐ球)へ切り替え、ラリーを長くして相手のエラーを誘う戦略に変更。
50代でも「配球の精度と選択」で勝負できることを体現しています。
年齢は戦術で上書き可能です。
– ポイント
– 軽補給+プレーの“遅速調整”で試合をコントロール
– シニアの強みは判断力と省エネの展開力
早朝マッチの準備ルーティン
試合2時間前に起床、軽食はヨーグルト+蜂蜜+水。
会場には早入りしてストレッチ→チューブで肩の外旋(※肩周りのケガ予防)→ショートラリーでタッチ確認。
パドルの表面摩耗やグリップの汗対策をチェックし、相棒リーとは10分だけゲーム速度の球で合わせます。
長いアップはせず“感覚合わせ”重視。
朝の硬さをほどき、初球から自分のリズムで入る準備を整えます。
– ポイント
– 可動域→タッチ→ゲーム速度の順でアップを組む
– 用具チェックは握り直しまで含めてルーチン化
まとめ
ハイメの実践は、メンタルと戦術の両輪で勝負するモデルケースでした。
感情の切り替え、役割分担、配球の精度、栄養とアップの具体化まで、真似できるポイントが多いです。
ケガは悔しいですが、判断の速さがキャリアを守ります。
次のコートで、さらに洗練された“省エネで強い”プレーを見られるのが楽しみですね。