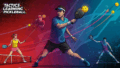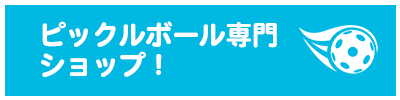米国の最新研究で目のケガ増加が示されましたが、データの網羅性には限界もあります。
そこで“数字の解像度”と“現場で効く対策”をセットで解説します。
保護メガネの選び方から立ち位置、反応練習まで、今日から実装できる形でまとめます。
なぜ増えている?最新研究を数で読む
解析はNEISS(※米国の傷害レジストリ)由来で2005–2024年を集計。
2014–2024年で目の負傷推計約3,100件、2021–2024年は年+約405件、2024年は約1,262件です。
母集団(競技人口)拡大が背景ですが、NEISSは全救急の一部のみ。
増加傾向は事実、比率は小、データは限定的という三点を同時に押さえます。
どのケガが多い?重症リスクもチェック
多い順は①眼周囲の裂創(約35%)②角膜擦過傷(約16%)。
いずれも擦り傷系ですが、前房出血=ハイフェマ(※眼内出血)、網膜剥離(約3%)、眼球損傷(約3%)、眼窩骨折(約2%)も確認。
発生の約7割は50歳以上。
軽症が多数派でも視機能に影響するケースがあるため、初期対応と予防が重要です。
速い×近いが危ない:道具進化と距離
最新パドル(※EVAフォーム等)の反発で打球初速〜約96km/hに到達するケースがあり、キッチン(※ノンボレーゾーン前縁)間距離約4.2mでは反応時間が極端に短くなります。
コート寸法は不変、道具は進化—このギャップが被弾リスクを押し上げます。
顔は常にボール側へ正対、目線先行を基本に、至近距離での反応練習を取り入れます。
原因の内訳と対策:ボール・転倒・パドル
内訳はボール直撃約43%/転倒約28%/パドル接触約12%。
対策は三面攻めが効きます。
- ボール直撃:キッチンで面を縦、顎を引く。ロブや速球は即時コールで共有。
- 転倒:シューズのグリップ点検、止まる→見る→動くの順でフットワーク。
- パドル接触:ダブルスは間隔50〜80cm維持、クロス優先で同時突入を回避。
短時間でもリアクションボレー30球×2セットで実戦耐性が上がります。
義務化は現実的?アイウェア選びの基準
義務化は運用課題(曇り・視界・コスト)が壁になりがちです。現実解はガイドライン+自主着用。選び方は:
- レンズ:ポリカーボネート(※割れに強い)、アンチフォグ。
- フレーム:フルリム+側面カバー、フィット調整可。
- 規格:国内JIS/国際ANSI相当を目安。
- 運用:室内/屋外でレンズ交換、汗対策に吸汗バンド併用。
見え方が悪ければ即交換が原則です。
今日からの安全アクション:現場チェック
- メガネ装着:練習から常用、曇り止め塗布。
- 立ち位置:キッチンで正対+膝軽く曲げる。
- 合図:アウト/ロブ/前の即時コール徹底。
- 反応練習:至近球のワンステップブロック×2セット。
- 転倒対策:シューズ・コートの滑り点検。
- 新人対応:初参加者に距離感と速度を最初に説明。
これだけで事故確率が下がります。
まとめ
増加は事実、重症は少数でもインパクト大、データは限定的——この三点を前提に現場の行動を変えます。
保護メガネの常用、正対と合図、反応練習と転倒対策でリスクは確実に下がります。
楽しく長くプレーするために、攻める前に守る仕組みを今日からアップデートしましょう。